東京都23区で、築1〜10年・駅から徒歩10分以内・1部屋タイプのマンションについて、2021年から2024年までの価格推移をチェックしました。
結果を見ると、平均価格は2021年の約5000万円から2024年には6200万円を超え、㎡単価も116万円から149万円へと大きくアップ。取引件数はおおむね1,000件前後で安定しており、「需要は強いけど供給は限られている」という状況が見えてきました。本記事では、この結果を踏まえて、投資家が知っておくと役立つポイントや注意点をわかりやすくまとめています。
目次
推移グラフ(年集計)
平均価格(年平均)
㎡単価(年平均)
㎡単価推移
東京都23区における1〜10年築、最寄駅から1〜10分の1部屋物件の㎡単価は、2021年から2024年にかけて着実に上昇しています。具体的には、2021年の116.2万円/㎡から、2024年には149.2万円/㎡に達し、3年間で約28.4%の上昇を見せました。この動向は、主に需給関係の変化、新築供給の減少、そして都市再開発の進行によるものと考えられます。
まず、需給関係についてですが、東京都心部では人口の増加とともに住宅需要が高まっています。特に若年層やファミリー層が都心に集中する傾向が強く、これが価格上昇を後押ししています。次に、新築供給の減少も影響しています。新型コロナウイルスの影響で工事が遅延したり、資材費の高騰により新規物件の供給が滞っています。これにより、既存物件の価値が相対的に高まる結果となりました。また、東京都内では再開発プロジェクトが進行中であり、新たなインフラ整備や商業施設の開発が進むことで、周辺地域の魅力が増し、価格上昇に寄与しています。
一方で、投資家が注意すべきリスクも存在します。まず、サンプル数の偏りが挙げられます。このデータは特定の条件を満たす物件に基づいているため、全体の市場動向を必ずしも反映しているわけではありません。また、駅距離や築年数のバラつきも影響を与える要因です。特に、駅からの距離がわずかに異なるだけで価格が大きく変動することがあるため、慎重な分析が求められます。
投資家に対する示唆としては、長期的な視点での投資が推奨されます。現在の価格上昇傾向を考慮すると、今後も安定した資産価値が期待できるため、自己利用兼用の物件を選ぶことも一つの戦略となるでしょう。しかし、短期的な利回りを狙う場合は、賃料実勢や管理状況の確認が不可欠です。マンション投資を行う際には、個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要であることを忘れないようにしましょう。
※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。
販売件数(年合計)
取引件数の推移
東京都23区における1〜10年築、最寄駅から1〜10分の1部屋物件の販売件数について、2021年から2024年にかけての推移を分析いたします。グラフによると、2021年の販売件数は1027件、2022年には1076件と増加しましたが、2023年には再び1027件に戻り、2024年は1062件と、全体的に安定した水準で推移しています。この動きにはいくつかの要因が考えられます。
まず、需給バランスが影響していると考えられます。特に2022年の販売件数の増加は、都心部における住宅需要の高まりを反映している可能性があります。新型コロナウイルスの影響により、リモートワークが普及したことで、都心での居住を希望する層が増加し、特に新しい物件の需要が高まったと推測されます。しかし、2023年に販売件数が減少した背景には、金利の上昇が影響していると考えられます。住宅ローン金利の上昇は購入意欲を抑制し、結果的に販売件数に影響を及ぼすことがあります。
次に、新築供給の動向も重要な要素です。東京都内では、特に再開発エリアにおいて新築物件の供給が進んでおり、これが既存物件の販売件数に影響を与えている可能性があります。新しい物件が市場に出ることで、既存物件の魅力が相対的に低下することも考えられます。さらに、季節性の要因も無視できません。通常、春先や秋口に物件の取引が活発になる傾向があり、これが年ごとの販売件数の変動に寄与している可能性があります。
リスクとしては、サンプル数の偏りが挙げられます。特定のエリアや築年数に偏ったデータに基づいて判断を行うと、全体の市場動向を誤解する恐れがあります。また、駅からの距離や築年のバラつきも考慮する必要があります。駅近の物件は需要が高い一方で、少し離れると需要が減少することが多く、立地による影響を無視することはできません。
投資家への示唆としては、長期的な視点での投資が望ましいと考えます。特に都心部の物件は安定した需要が見込まれるため、自己利用兼用の物件としての購入も検討に値します。ただし、物件選びにおいては、賃料実勢や管理状況の確認が不可欠であることを強調いたします。マンション投資を行う際には、個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要です。
※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。
スタッフコメント
今回のデータをざっくりまとめると、「駅近・築浅の1部屋マンションは、やっぱり強い!」という一言に尽きます。わずか3年間で平均価格は25%以上アップ、㎡単価にいたっては約30%も上昇していて、東京都23区の需要の底堅さを改めて感じました。
ポイントは、需要はしっかりあるのに供給はあまり増えていない、ということです。販売件数は毎年だいたい1,000件前後で落ち着いていて、急に物件が増えているわけではありません。つまり「欲しい人が多いけど、数が限られている」から価格が上がりやすいんですね。さらに、ここ数年は新築の供給が減っていることや、資材費の高騰もあって、築浅の既存物件がより注目されるようになっています。
また、エリアによっては再開発が進んでいて、商業施設や交通インフラが整うことで「資産価値が落ちにくい物件」として見られるケースも増えています。こうした動きも価格を押し上げる要因になっていると思います。
ただ、いい話ばかりではなく注意も必要です。今回のデータは「徒歩10分以内」「築10年以内」という条件で絞っているので、どうしても数字は高めに出やすいです。同じ築10年でも管理状態や修繕計画によって価値は全然違いますし、駅まで10分といっても路線や周辺環境で利便性は大きく変わります。「データ上は強いから大丈夫」と思い込みすぎるのはちょっと危険ですね。
投資を考える人にとって大事なのは、やっぱり「長く持つ」視点です。短期で売買して利益を出すよりも、安定した賃料収入を得ながら資産を育てていくほうが、このエリアには合っていると思います。そのためにも、実際の賃料相場や入居需要をしっかり調べてから判断するのがポイントです。
もうひとつのおすすめは「自分や家族が住んでもいい」と思える物件を選ぶこと。出口戦略の幅が広がりますし、いざという時に安心です。東京都23区は依然として人の流入が続いていて、需要が強いので長期的に資産価値を保ちやすいと言えます。ただし、物件ごとにリスクや強みはバラバラなので、最終的には現地を見て「ここなら安心」と思えるかどうかが決め手になります。
まとめると、「駅近×築浅×1部屋」の組み合わせは今後も投資先として注目度が高いけれど、数字だけに頼らず、物件の実態や自分の投資スタイルに合うかどうかをきちんと見極めることが成功のカギになると思います。
グラフのデータは国土交通省の「不動産情報ライブラリ」をもとにしています。グラフ下の解説は、不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解で表示させており、必ずしも正しいとは限りません。













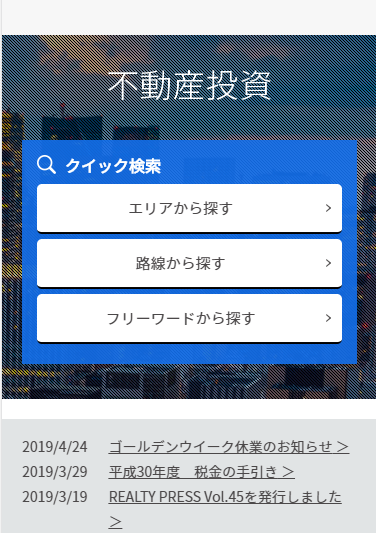
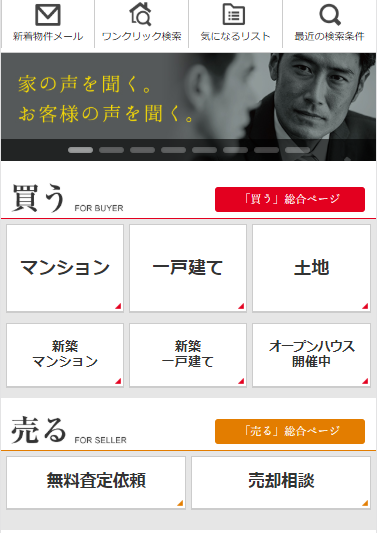

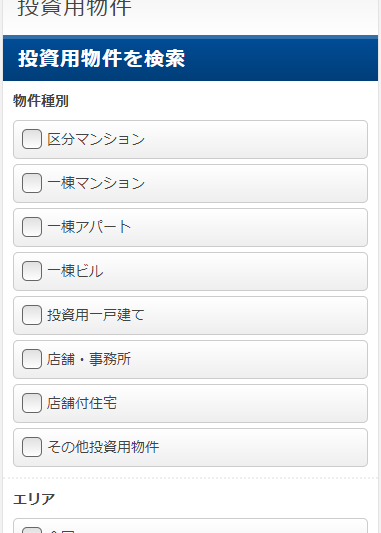




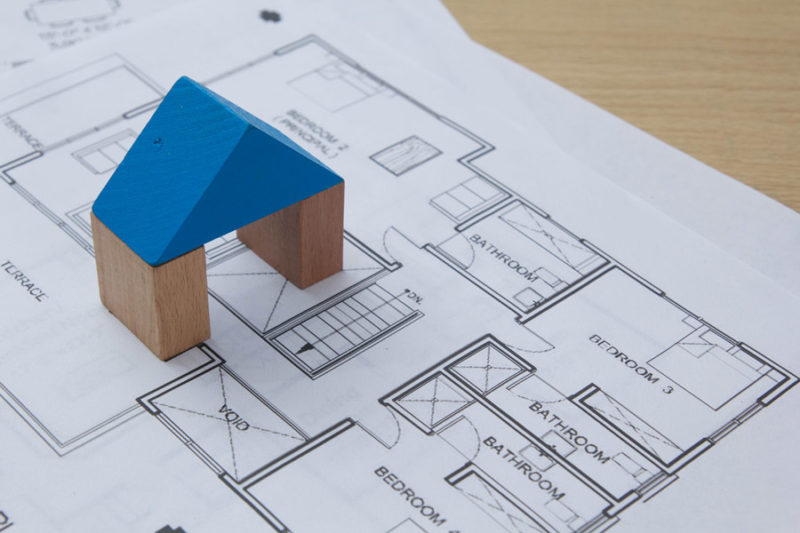
価格推移
東京都23区における1〜10年築、最寄駅から徒歩1〜10分の1部屋物件の価格推移を2021年から2024年まで分析した結果、平均価格は2021年の4981万円から2024年には6226万円へと上昇していることが明らかになりました。この価格の上昇は、主に需給バランスの変化、新築供給の減少、そして再開発の進展によるものと考えられます。
まず、需給バランスの変化についてですが、近年の東京都心部では、特に若年層や単身世帯の増加に伴い、1部屋物件への需要が高まっています。これにより、限られた供給の中で価格が上昇する傾向が見られました。次に、新築供給の減少も影響しています。新型コロナウイルスの影響で建設が遅れたり、資材費の高騰が続く中、新築物件の供給が減少し、既存物件の価値が相対的に上昇しています。また、再開発プロジェクトの進行により、特定のエリアでの物件価値が上昇することも影響を与えています。これらの要因が重なり、価格は安定的に上昇していると考えられます。
しかしながら、投資を行う際にはいくつかのリスクや留意点も存在します。まず、サンプル数の偏りがあるため、特定のエリアや物件において価格が急激に変動する場合があります。また、駅からの距離や築年数のバラつきが、物件の実際の価値に影響を与えることも考慮する必要があります。このため、エリアごとの特性や市場の動向を十分に理解した上で投資判断を行うことが求められます。
投資家に対しては、長期的な視点での資産形成をお勧めいたします。短期的な利益追求も可能ですが、安定した収益を得るためには、自己利用兼用の物件としての購入も視野に入れると良いでしょう。マンション投資を行う際には、個別物件の賃料実勢や管理状況の確認が必要ですので、十分な調査を行うことをお勧めいたします。
※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。