東京都の都心3区(千代田区・中央区・港区)は、単身者やDINKS層を中心に安定した需要が見込まれるエリアです。特に築年数11〜15年の1LDKクラスを中心としたマンションは、利便性と資産性の両面から投資家に注目されています。
本記事では、2021年から2024年にかけての平均価格、㎡単価、そして取引件数の推移をグラフで整理しました。都心部における需給バランスや新規供給の動きに加え、投資判断に影響するリスク要因についても解説しています。データを基に、市場の現状と今後の投資戦略を検討する参考にしてください。
目次
推移グラフ(年集計)
平均価格(年平均)
㎡単価(年平均)
㎡単価推移
東京都の都心3区における11〜15年築の1部屋物件の㎡単価推移を見ていきます。2021年の㎡単価は122.6万円/㎡でしたが、2022年には148.9万円/㎡に上昇しました。2023年は150.3万円/㎡と微増し、2024年には173.5万円/㎡に達する見込みです。この数値は、都心エリアにおける需要の高まりを反映しています。
主な要因として、需給バランスの変化が挙げられます。特に、都心部への移住希望者が増加していることが影響しています。また、新規供給が限られているため、既存物件の価値が上昇しています。しかし、リスクとしては、築年数や駅距離によるサンプル偏りが考えられます。これにより、実際の投資判断には慎重さが求められます。
投資家にとっては、長期的な視点での投資が有効と考えられます。市場の動向を見極めつつ、個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要です。
※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。
販売件数(年合計)
取引件数の推移
東京都の都心3区における、築年数11〜15年、最寄駅徒歩1〜10分、間取1部屋の物件に関する取引件数の推移を見ていきます。2021年から2024年までのデータによると、販売件数は108件から114件へと増加しています。この期間中、特に2023年には110件に達し、2024年にはさらに増加が見込まれています。
この取引件数の増加には、主に需給のバランスと新規供給の影響が考えられます。需給のバランスが改善されることで、物件の取引が活発化し、特に都心部では需要が高まっていることが要因の一つです。また、新規供給の増加も影響しており、特に築年数11〜15年の物件は、比較的新しいため、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
一方で、リスクとしてはサンプル偏りが挙げられます。特定のエリアや駅近物件に偏ったデータは、全体の市場動向を正確に反映しない可能性があります。これにより、投資判断に影響を及ぼすことも考えられます。
投資家にとっては、長期的な視点での投資が望ましいと考えられます。都心部の物件は、安定した需要が見込まれるため、長期的な資産形成に寄与する可能性があります。ただし、個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要です。
※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。
スタッフコメント
都心3区における築11〜15年の1LDKマンションの動向をデータで見ていくと、まず目立つのは価格の上昇トレンドです。2021年に6,100万円台だった平均価格が、2024年には8,700万円台まで伸びており、約40%近い上昇となっています。この背景には、新築供給が減少していることと、都心への人口流入が継続していることが挙げられます。駅徒歩1〜10分という利便性の高い条件に該当する物件は特に人気が高く、結果として築浅〜中堅の物件でも価格が強含みになっているのが実情です。
㎡単価で見ると、2021年に122万円/㎡だった水準が、2024年には170万円超に到達する見込みで、こちらも堅調に推移しています。価格総額だけでなく、㎡単価ベースでも上昇していることから、単なる物件サイズの影響ではなく、資産としての評価自体が底上げされていると考えられます。特に、都心部の生活利便性・交通アクセスは国内外の需要を支える要因となっており、賃貸ニーズ・売却ニーズの双方において市場の厚みがある点は投資家にとって安心材料といえるでしょう。
一方で、取引件数をみると増加傾向が確認されますが、年によって件数の振れ幅があるため注意が必要です。築11〜15年の物件は「まだ新しい」と評価される一方で、新築プレミアムが薄れ、実需層にも手が届きやすい価格帯に入るため、売買が活発になる傾向があります。2021年の108件から2024年の114件への増加は、市場の流動性が保たれていることを示しており、投資家にとっては出口戦略を考える上でも有利な条件といえるでしょう。
ただし、リスク要因を軽視してはいけません。例えば駅距離が同じ「1〜10分圏内」としても、実際には1分の物件と10分の物件とでは資産価値に差が出やすく、価格形成にも影響します。また、築年数の区切り方によるデータの偏りや、取引件数の母数が限られている点も考慮する必要があります。短期的な売買で利益を狙うよりも、賃貸需要の強い都心部の特性を活かして、中長期的に安定収益を確保する戦略が現実的でしょう。
まとめると、都心3区の築11〜15年・1LDK中心のマンションは、供給減少と需要増加のバランスによって資産価値が堅調に推移しているカテゴリーです。投資家としては、価格上昇の恩恵を受けつつも、物件ごとの条件(駅距離・管理状況・賃料実勢)をしっかり精査し、将来的な出口戦略を描いた上で購入判断を下すことが求められます。グラフの数値はあくまで全体傾向を示すものですが、その裏にある需給の力学を理解することで、より戦略的な投資判断が可能になるでしょう。
グラフのデータは国土交通省の「不動産情報ライブラリ」をもとにしています。グラフ下の解説は、不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解で表示させており、必ずしも正しいとは限りません。必ずマンション投資の専門家にご相談ください。














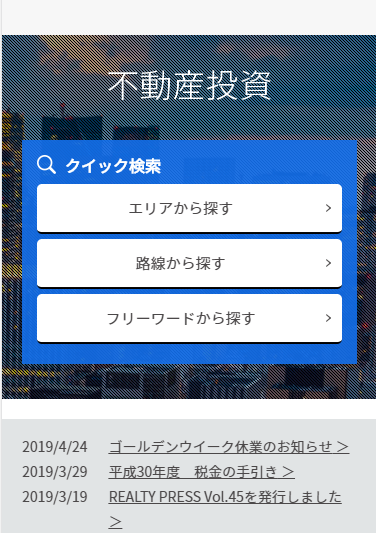
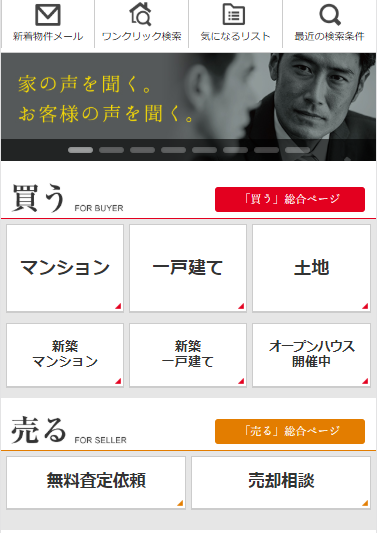

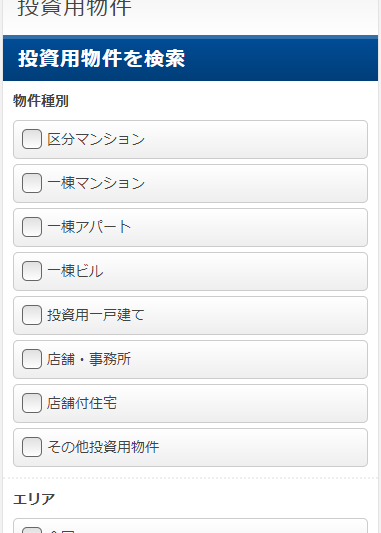




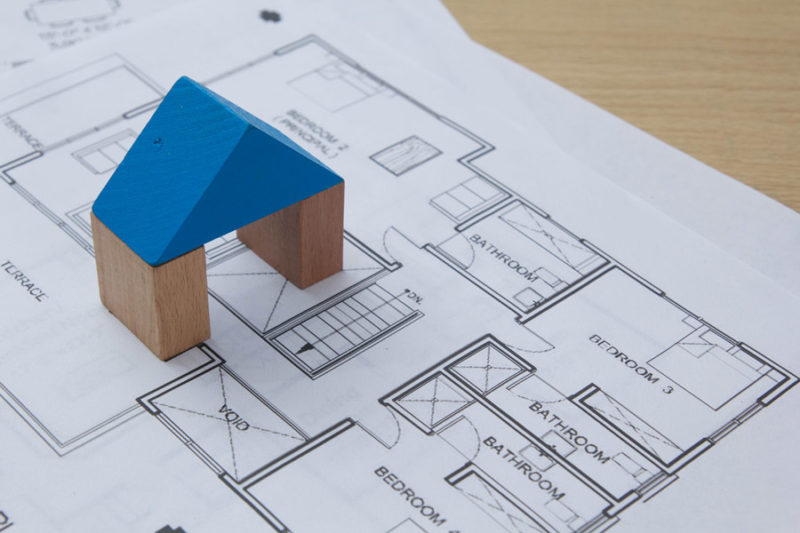
価格推移
東京都の都心3区における築年数11〜15年の1部屋物件の価格推移を見ていくと、2021年の平均価格は6,109万円から始まり、2024年には8,715万円に達しています。この期間における価格の上昇は、主に需給バランスの変化と新規供給の減少によるものと考えられます。特に、都心部では人口の流入が続いており、1〜10分圏内の物件に対する需要が高まっています。一方で、新規供給が限られているため、既存物件の価格が押し上げられる結果となっています。
ただし、投資を検討する際にはリスクも考慮する必要があります。特に、駅からの距離や築年数の偏りが影響を及ぼす可能性があるため、慎重な判断が求められます。例えば、駅からの距離が1分の物件と10分の物件では、価格に大きな差が生じることがあります。投資家にとっては、長期的な視点での物件選定が重要です。市場の動向を見極めつつ、自己利用も視野に入れた選択肢を検討することが望ましいでしょう。個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要です。
※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。